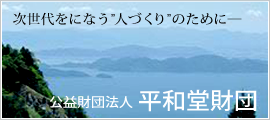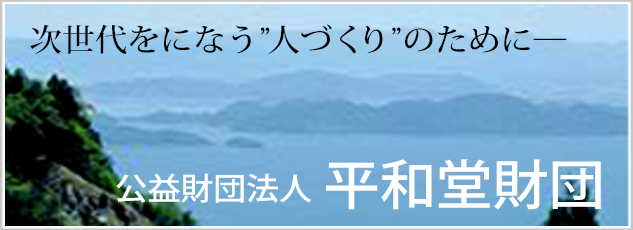甲賀木の駅プロジェクト「森林を愛する人を増やそう計画!!」 /甲賀木の駅プロジェクト運営委員会
事業の概要
新規事業として、森林所有者を対処としたチェーンソーと伐採技術講習会の開催を年に4回程度、また一般市民対象の森林環境教育イベントを年2~3回開催します。

2017年7月30日、甲賀木の駅プロジェクトの「上下流連携の森づくりの集い」に伺いました。会場は滋賀県甲賀市甲賀町神という地域の人工林です。甲賀木の駅プロジェクトが託された、スギ、ヒノキの人工林には、間伐の成果で明るい広場もあります。そこに大阪府豊中市と地元甲賀市などからの小学生とその保護者が集い、林業を体験し森の中で遊ぶというイベントです。このイベントは今年で15回目ということです。

木製の橋は手作り。坂道を登ったところが受付テントです。

オレンジ色のユニフォームが、甲賀木の駅プロジェクトと甲賀愛林クラブのメンバーです。甲賀愛林クラブの中のプロジェクトチームとして、甲賀木の駅プロジェクトがあります。
そのほかにも かふか林業研究会、大原自治振興会、甲賀市役所、滋賀県森林整備事務所、豊中からはとよなか消費者協会とアジェンダ21など、立場の異なる多くの組織が協力しています。
もっと多い年もあるそうですが、今回は豊中市から21名、滋賀県内から29名、そしてスタッフは50名と、総勢100名が参加しています。
受付ではヘルメットと軍手、イベントのしおりなどをもらいます。ヘルメットは必ず装着のこと!

大人が受付を済ませている間、子どもたちは手作りのロープ遊具に夢中。立木にロープを2本渡してあるだけのシンプルなものですが、本当に楽しそうです。

朝10時、開会式です。
甲賀愛林クラブ会長の会長、北澤さんと、来賓のあいさつの後、今日のスケジュール、注意事項などを進行役の大原さんが伝えて開会式が終了しました。

プログラムの最初は、森づくり体験です。班に分かれ、先に説明とデモンストレーションを見学。
その後、人工林に入り班ごとに実際にヒノキの皮むきに挑戦します。明るい広場から人工林の奥に入ると、まだ間伐されていないためにかなり薄暗く感じます。

五班のスタッフは、坂口さんと中尾さんのお二人で、参加者は親子3組です。
坂口さんは「年は取ってるけど、山に入ったら負けへんで!」、中尾さんは、甲賀愛林クラブで今一番若いメンバーで「農業をしながら、父の道具で山仕事をやっています」と自己紹介。

間伐する木には印がついているので、その木に巻いてあるビニールテープを外すところから始めます。このテープはシカに皮を食べられないように巻かれているそうです。

テープを取り除いたら、木の根元にノコギリで切れ目をつけていきます。皮の部分だけを切りながらくるりと一周します。

その切れ目にヘラを差し込み、皮を少し浮かせたら、手でひっぱります。すると、皮だけが上へむけていくのです。

お母さんと一緒にひっぱれ。

全部皮を取り除かれた木の幹は、つるつる!
表面から水がしみ出してきて、まだ生きていることが感じられます。
この状態になると、木は根から水分や栄養を上まであげることができないので、次第に立ち枯れていき、枯れた幹は乾燥します。乾燥した木を伐採すると、木材として使うのに乾燥の手間が省けるうえに、運び出しの負担も軽くなるそうです。
中尾さん「皮むきは山仕事の素人でも簡単にできますから、楽しく山の整備に参加してもらえます」。確かに、あるお父さんは「4本むきました!」と意気揚々と報告するほど。ほかの皆さんも夢中になって取り組んでいました。
お子さんと楽しそうに作業をしていた、甲賀市内の男性は「こういう山仕事もあんねんで、と子どもの仕事の選択肢になればいいな、という気持ちで参加しました」とのこと。本当にこれが山仕事への入り口となるといいですね。

続いては、伐採のデモンストレーション。あらかじめロープを結んでおいた木をメンバーがチェーンソーで切ります。その時、子どもたちがロープを引っ張って倒す、というもの。

倒す方向を決めるため「受け口」と「追い口」という二つの切り込みを入れました。「OK」サインが出たら、子どもたちがロープで引っ張りました。滑車で方向を変えているので木は引き手の方向には倒れません。

見事、予定の方向に木が倒れました。一同拍手喝采です。子どもたちの記憶に残るシーンだったのではないでしょうか。

お昼の時間となりました。大原自治振興会の皆さんが準備を担当。薪で焚いた白いご飯と炊き込みご飯があります。

会長さん自ら獲ってきたというシカ肉の鉄板焼き。

地元からの差し入れの松茸は、豚汁と炊き込みご飯に。

山のご馳走をいただきます!

突然、通り雨が。雨宿りしながらの昼食タイムとなりました。

雨も上がり、自由に山仕事を体験する時間です。
こちらは、低学年の子ども向け薪割り機。木を刃の上に置き、金槌で叩いて割っていきます。高学年の子どもは、別のコーナーでナタの薪割りにチャレンジです。最初に基本を教えてもらって思い切り振り下ろし、上手に薪が割れた時は得意そうでした。
ほかにも紙手裏剣を的に入れるコーナー、ロープで作ったブランコなどの森のプレイパークコーナーがあり、子どもたちは元気いっぱいに遊んでいました。

途中、チェーンソーアートの実演が始まりました。多賀町の林研グループの樋栄さんが、樹齢二百年という木をチェーンソーで刻んでいきます。

途中、別の丸太を半分に割ったものを切り始めました。違うもののようです。何でしょうか?

あらかじめ刻みを入れられた丸太が2個置いてありました。
そこへ、さっきの半分に割った丸太を置くと、ぴったりはまります。


立派なベンチができあがりました。

そして、チェーンソーアートのほうは、枝に乗ったフクロウが完成しました。子どもたちも興味津々です。

次はカブトムシ探しです。会場から少し歩いて行った先のシイタケ園が会場です。見つけたカブトムシは持ち帰っていい、というルールなので、みんな目の色を変えて探します。

「昨日、スタッフが70匹くらい放した」という話を聞いていたので、私もすぐに見つかるだろうと思って探したのに、ちっとも見つかりません。

3匹見つけた子もいましたが、全く見つけられなかった子も多いようでした。

元の会場に帰ってきたら気分を変えて、チェーンソーアートのフクロウを賭けた、子どもたちによるジャンケン大会です。優勝者はとてもうれしそうでした。ベンチは大人のオークションとして競り落とされました。

閉会式では、豊中市からのアジェンダ21の茨木さんが「このあたりで降った雨が染み込んで琵琶湖に注ぎ、ダムの水となって、下流に住む私たちの水道水になります。うちに帰って水道の水を飲んだら、今日、上流の森をきれいにしたなあ、と思い出してください」とあいさつしました。
甲賀木の駅プロジェクトの委員長、竹中島さんのあいさつをもって閉会となりました。
イベントは終始、軽妙な大原さんの司会のもと、なごやかに進行。でも、注意すべきところでは「山で走ったら、転んで危ないよ」「必ずヘルメットをかぶったらアゴの下でしっかり留めて!」など、的確な指示が出されていました。各保護者の監督もあり、子どもたちが勝手に暴走せず安全に体験できました。
今回のイベントでのスタッフの皆さんの願いは、小学生たちが大きくなって山に入ってほしい、ということです。そのためによく考えられたプログラムだと感じました。子ども時代の体験は、大人になってからでも思い出すことができます。将来、林間に子どもの歓声が聞こえるよう、甲賀木の駅プロジェクトの皆さんには、これからもずっと長い期間で活動を続けていただきたいと思いました。