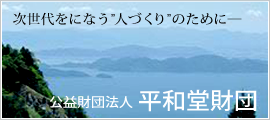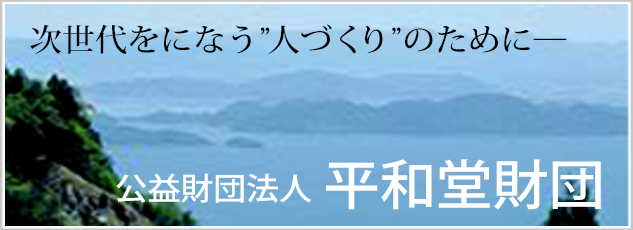エコ水車で夜道も明るいまちづくり /のとがわエコ水車の会
事業の概要
東近江市の能登川町には、豊富な水をたたえた小川や用水路が縦横に流れていますが、夜は暗く危ない場所が多いです。この事業は、廃棄自転車を活用し水車をつくり、水の流れにより発電させ水辺を明るくするとりくみです。八幡工業高校の生徒さんと一緒に、さらなる技術アップと性能のいいエコ水車づくりにとりくみ、水車を通して河川美化を訴えながら、設置できる場所を増やしていきます。

訪問2012年度 のとがわエコ水車の会
12月11日、夏原グラント2012の採択団体の「のとがわエコ水車の会」が、近江八幡工業高校のみなさんと一緒にエコ水車の製作をされていると聞いて、工業高校を訪問させていただきました。

【近江八幡工業高校】
エコ水車は、廃棄された自転車の車輪と発電機を活用した水車発電で灯りをつくり、防犯のために夜の水辺や道を照らすという2重のエコを兼ね備えています。

【地域の用水路を回るエコ水車】
水車の製作を始めたヒントは、用水路の水がただ流れているのがもったいない、そして放置自転車の廃物利用できないかということです。何回も試行錯誤で改良を加え、現在15機目を製作中。1年間に約1万km回るためすぐに部品がだめになるので、常にパワーアップを図りたいとのことでした。河川法があるので農業用水路しか設置できません。農業用水路は、地元の理解と許可があれば設置可能なのだそうです。

【学生のみなさんと知恵と技術を交流】
近江八幡工業高校と一緒に行っているのは、お互いの知恵やノウハウを出し合うためで、特に若い方のアイデアは新鮮なのです。もっかの課題は、昼間に起こした電気を夜に使うための蓄電のしくみと、水面の高さの変化に応じて軸受けの高さを変える。この2点だそうです。

【高校で製作中の改良型エコ水車】
既に改良されていたのは、水車を支えるフレームです。ずっと木の枠だったので金属にしたかったのですが、金属だと溶接技術や機械が必要なのです。工業高校にはそれがあります。たまたま繋いでくれる方がいたので、協力し合えるようになったそうです。

【ミーティング中】
高校生の工夫はすごいものがあります。ミーティングで出たアイデアを、すぐに材料に手を加え作っていくのです。試行錯誤ではありますがだんだん形になっていく。ものづくりの基本は試行錯誤なのだそうです。

【軸受けを溶接】
この日、1つのグループは、軸受けの高さを変えるための部品の加工をおこなっていました。軸受けを溶接し形にする、軸受け設置のための平板を長さに合わせて切りとる、平板に穴をあける印をつける。金属ドリルで穴をあける。グループで分担しながら、必要な機械が備え付けてある部屋をどんどん移動します。

【平板の加工】
もう1つのグループは容量にあったバッテリーのメーカーを調べていました。蓄電のためには交流を直流にするということと、一番の課題は、バッテリーの過充電がおこるとバッテリーが持たなくなるのでその工夫を考えることです。また、LEDの電球が使えないかなども話し合っていました。

【蓄電の工夫】

【のとがわエコ水車の会の村田さんと学生さん】
のとがわエコ水車の会では、この水車をいろいろな形で応用していきたいとのことです。あちこちで、そしていろいろな目的で、エコ水車が使われていくといいですね。今後の広がりが期待されます。
みなさん、がんばってください。