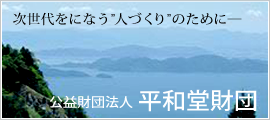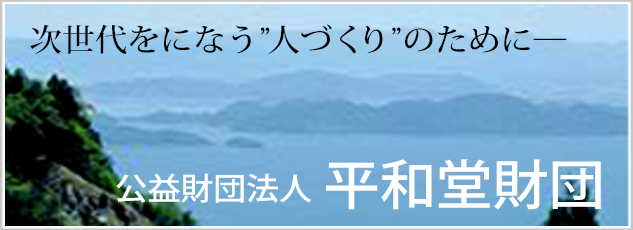小塩山のコナラ林の若返りを進め、カタクリ・ギフチョウ保全と薪資源の活用を図る /西山自然保護ネットワーク
事業の概要
京都市西京区にある小塩山は、京都府か京都市以南で唯一のカタクリ群生地であり、ギフチョウ育成地です。1960年代から炭焼きなどが行われなくなり、コナラが育ちすぎています。そのコナラを伐採して若返りを図るとともに、現在、会員と市民の協力で張っている獣害ネットを張りなおすことを目指して活動中です。伐採した樹木は薪にして運び出して利用します。

2019年10月27日、日曜日の午前中に京都市南区のJR桂川駅から、事務局長の坂梨孝文さんとともに会計の伊藤弘さんの車に乗せてもらい、西山自然保護ネットワークの活動を訪問しました。

桂川駅のデッキから見えている西の方向の山には鉄塔がいくつも立っています。大阪から京都への電波の中継地点だそうです。

関係者以外立ち入り禁止の府道を車で登り、電波塔の近くで降りて、小塩山にある西山自然保護ネットワークのフィールドに歩いていきました。小塩山の北斜面には、カタクリの自生地があり、カタクリとギフチョウの生息環境を整える活動をしています。西山自然保護ネットワークのこの活動は地主さんたちから許可を得ているので、山頂までの府道の通行も可能なのです。

到着してみると、メンバーが集合して、これから森林整備作業に出かけるところでした。
今回は西山自然保護ネットワークのメンバーに加えて、大学生のボランティア団体、IVUSA(NPO法人 国際ボランティア学生協会京都)から4名が参加。

防獣ネット外の尾根に、活動の拠点の広場があり、小屋に道具がしまわれています。

伊藤さんが持っている金具は、モグレーヌという名前のイノシシ防御柵です。

防獣ネットのすそからもぐりこむイノシシを防ぐため、このように土に刺しておきます。一枚が90cmなので、防御する箇所が多すぎて、一か所を防ぐと別のところをもぐられ、イタチごっこだそう。

少し離れたところに設置された、簡易トイレ。これは女性がボランティアに参加する時のために新たに購入したそうです。山奥でトイレがない場所では必要ですね。

会の代表の宮崎 俊一さんと、会計の伊藤さんが活動フィールドを案内してくださいました。
鹿やイノシシの食害がひどく、それを防ぐために防獣ネットを張り巡らせ囲んだ場所が4カ所あり、それぞれに「炭の谷」「鏡の谷」「御陵の谷」などの名前が付けられています。

昔からコナラやクヌギは、貴重な燃料として森に植樹され、定期的に伐採されては炭に加工されていました。京都の西山で生産された炭は、京都の町に売られていきました。
しかし1960年代以降、燃料がガスや電気に取って代わられ、木炭はどんどん需要が少なくなっていき、同時に炭焼きが行われなくなりました。クヌギなどの木々は手入れをされないまま成長し過ぎてしまいました。
伐採されない森では広葉樹が生えて生い茂り、夏、真っ暗になってしまった森では、カタクリも、ギフチョウの食草であるミヤコアオイも生えることができません。各地の自生地は消滅していく一方でした。
そこで、西山自然保護ネットワークでは成長しすぎたクヌギやコナラ、そして他の常緑樹を一度伐採してしまい、その後に苗木を植えることで、明るい森を再生する活動を続けています。明るさを取り戻した谷では一面にカタクリが咲くようになり、今ではワンシーズンに2000人が花を見るために訪れているそうです。

具体的な活動としては、成長しすぎたクヌギやコナラ、その他の常緑樹などをチェーンソーで伐採。

倒した木を玉切り(ある程度同じ長さに輪切りにすること)。

玉切りした木を割って薪に。

薪がたまると、背負って舗装路まで降ろし、ある程度溜まるとトラックで回収し京都市内に運んで薪ストーブ愛好家に販売します。そのお金は地主さんの収入となるそうです。エネルギーの地産地消や、地域の活性化にも役立てているんですね。

これは舗装路のそばまで、薪を背負って降りてきたところです。IVUSAの学生とメンバーが交代で運んでいました。急傾斜なので他の道具が使えず、人力に頼るしかないそうです。
活動に使用する薪割りのための斧やモグレーヌ、簡易トイレの購入、また、コナラなどの伐採と玉切りをしてもらう林業専門家への委託費と学生の交通費と謝金など、夏原グラントの助成金が使われているとのことでした。

明るくなった森には、下草がどんどん茂ります。防獣ネットで鹿やイノシシが入ってこられないため、ほっておくと、また背丈ほども生い茂ります。定期的に人の手で草刈りしなければ、苗木が枯れてしまうそうです。

「ほら、これがミヤコアオイで、ギフチョウの食べ物になる草です」と見せてもらいました。
京都市内では、ここが唯一のカタクリ群生地であり、また唯一のギフチョウの生育地とのこと。
草刈り作業は主に女性メンバーが担当されていました。
女性の皆さんにこの活動に参加するきっかけを尋ねると「山歩きが好きなので、グループのリーダーに連れられてカタクリの花を見にここに来た時、『一緒に活動しませんか?』と誘われました。それで『私にできることがあるのならやります!』と参加したんですよ」と笑顔で答えてくださいました。

「炭の谷」をぐるりと見てから、今度は小塩山にある淳和天皇陵へ。それからその下に位置する「御陵の谷」に案内してもらいました。

谷はそれぞれ鹿よけのネットでぐるりと囲んであります。人も立ち入らないよう、杭を打ってロープで囲んであるのですが、ここでは切れていたのですぐに応急の修理を。

「御陵の谷」の中も、4月にはカタクリの群落がみごとに咲くそうです。
カタクリが咲く時期には、ネットワークのメンバーが交代で「花ボランティア」の巡回を行います。最初は「パトロール」と称してカタクリの花を見に来た人が花を採ったり、踏んだりしないように監視していたそうです。でも、2006年から「花ボランティア」に変えたそうです。
代表の宮崎 俊一さんは「花ボランティア」の役割について「見学に来た方との対話がメインの仕事です。この会の活動がなぜ必要なのか、どうやってカタクリの群落を維持しているのか、そして一緒に花ボランティアとしてカタクリを守りませんか?などと話して入会と寄付を募りながら、活動に加わってもらっています。」と教えてくれました。
聞けば、こうして増やした会員は現在400人! また、4つの谷をぐるりと囲んで張る防獣ネットは、延べ1840mにも達しています。これらの費用226万円は、見学の方々からの寄付と会員からの会費、ごく一部は京都府からの助成金だそうです。
「対話の勉強に毎年『花ボランティア学校』をおこないます。役になりきるロールプレイで練習もしています。もちろん、花のことや小塩山の歴史、データなどの教科書を作り講義があります。『花ボランティア学校』を受講した人だけが『花ボランティア』になることができます。」と宮崎さん。さっきお聞きした、草刈りをされていた女性は、まさに「花ボランティア」との対話によって会に参加されたわけです。

伊藤さんが「花ボランティア」の時に使う資料「花ボランティア手帳」のファイルを見せてくれました。地図や説明などがいっぱいで充実していました。これなら、何を聞かれても安心ですね。
「花ボランティア」の活動は、メンバーの固定化や高齢化による会員の減少、後継者不足などに悩む団体の問題解決のためのヒントになるかもしれません。

山を下る時は、大原野から京都市内が一望できる素晴らしい景色も見られました。
西山自然保護ネットワークの皆さんが、これからも長く活動を続けていかれますよう、期待しています。