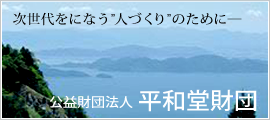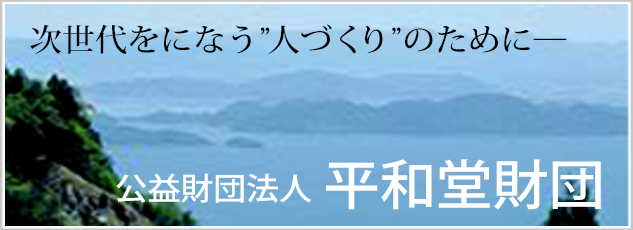ニホンミツバチの蜜源の谷づくり事業 /沖島里山保全の会
事業の概要
滋賀県近江八幡市の沖に浮かぶ沖島をフィールドに、2019年度から夏原グラントファーストステップ助成を受け「沖島の山道整備事業」を開始し、台風による倒木の除去や、耕作放棄地のある湯ケ谷(やんたん)の整備活動を2年間行ってきました。今回の事業では、引き続き湯ケ谷の耕作放棄地や周辺の湖岸の整備を行い、ニホンミツバチを捕獲し飼育も行います。整備した場では環境学習や採蜜体験などが可能なので、将来的には会が自立するための資金づくりにもしていけたらと考えています。

2022年1月22日、沖島里山保全の会の活動「二ホンミツバチの蜜源の谷づくり事業」を訪問してきました。
沖島里山保全の会は、日本でも唯一の淡水湖上の有人島である沖島で、荒廃した里山と里うみ(琵琶湖)の環境を改善することで豊かな生態系を守ることを目的に活動しています。この島も少子化・高齢化の波にさらされ田畑の耕作放棄がすすみ、獣害も大問題となっています。メンバーは、月1回の整備に近隣の市町から、そして遠く県外から通ってきておられます。この事業では、作業小屋を修理して道具類を保管できるようにすることと休憩できる場所の整備、藪化した土地の整備を行います。
沖島に魅力を感じて、地域おこし協力隊として関わり始めた会の代表でもある山角さんは、「私は3年前から沖島住民です。沖島に移住希望ありきで地域おこし協力隊になりました。」と笑って話してくださいました。藪化して荒れた土地を整備し始めた頃よりもだんだんと島の人たちとも打ち解けるようになり、活動への理解も広がり、深まっているとのことです。

代表の山角さんが集合場所である堀切港へ、対岸から出発した船でメンバーをお出迎え。今日は、7人のメンバーが参加しています。いつもよりは少なめの少数精鋭だそうです。折り返す船に一緒に乗って、今日の作業についての打合せをしているうちに10分ほどで沖島漁港につきます。この日は曇り空ではあるものの、風はなく、穏やかな湖面を進んでいきました。

沖島漁港から活動のフィールドである湯ヶ谷(ヤンタン)まで、歩いて30分ほどだそうです。各自が持ってきた作業用の道具などを手に、雑談をしながら歩いていきます。山に登っていくのではなく、平坦な道を湖辺に沿って歩いていくので、みなさんの足手まといになるこなくついていくことができました。
歩いていたメンバーの方とお話ができました。「私は、この沖島に遊びに来た時、島のことを聞きたくて声をかけたのが山角さんだったんです。山角さんと話しているうちに、ここで里山整備のために草木の伐採や整地などをされていると聞き、それじゃあ私も一緒にやろうかしらと思ったんです」とのこと。その瞬間、「もう、運命ですね」と答えてしまいました。出会いってすごいです!

途中、沖島小学校前を通り、活動フィールドである湯ヶ谷に到着しました。入口に作業のための道具が保管されている小屋があります。この小屋の修復は夏原グラントの成果のひとつです。「作業によって必要な道具は違うので、それはその時に応じて持ってきたりしますが、基本的な道具はここに保管できるようになりました」とのことです。

今日の作業に使う草刈り機、シャベル、カマなどを出します。
作業の最終確認です。前回までの作業で刈った枝や草木を、「今日は風がないから燃やしていこう」ということになりました。おいてある場所からどんどん運んで積んでいきます。

なるべく枯れた枝を選び燃料を撒き、火をつけます。湿った草木が多いのか、なかなか火は安定しませんでしたが、しばらくすると炎が上がってきました。

火も安定してくると、「ああ、これなら芋を持ってくればよかった。いい焼き芋ができたのに」「次回、風がなかったら焚火をして芋を焼こう」と話がまとまりました。

この場所に、放置された農機具がありました。前々から作業しているときに何とかしたいとは思っていたけれども、ずっとそのままでした。藪の中に隠れていた時は気にならなかったけれど、周りがきれいに整備されてくると、この農機具のある場所が気になりだしてきたと、みんなが話し始めました。「動かすだけならいいんじゃないか」。

シャベルを咬ませてハンドルを握ってみると、動きそうな気配。「よし、こっちの角の方に動かしてみよう」ということになりました。そうこうしているうちに、離れ離れで作業していた他のメンバーたちも集まってきました。
どちらの向きへ、どう動かすか。タイヤの下に板を差し込んで動かしながら、近くにあるものを使いながら、知恵を絞って、力を合わせて農機具を少しずつ動かしていきます。
まずは埋まっている状態から脱するために横に転がし、少しずつ方向を変えていきます。

農機具はゴロゴロと前後左右上下と向きを変えながら予定していた場所へ。

声を掛け合いながら作業を進めているみなさんを見ながら、力と知恵を合わせて動いていくことがすごいなあと思いました。
農機具の移動がおわると、またそれぞれの作業に戻っていくみなさん。間合いが素晴らしいです。
作業は、水路の清掃、

絡まっているクズのつるを引っ張り出して刈り、

竹笹を刈り、

クズを除去するために、薬剤がしみこんだ爪楊枝状の除草剤を打ち込んだり。

みなさんの作業が進んでいきます。
今日作業をしている棚田跡の上の段には、みかんがたくさん実をつけています。

「ここも最初は藪だったんだけど草木を刈って整備したら、みかんがなるようになりました。やはり手入れをすると、それに応えてくれるもんだなあと思ってうれしくなりました」とのことです。近くで二ホンミツバチを見かけることはあるけれども、この谷にはまだ飛んできていないそうです。それでも整備をしなければ飛んでくることはないので、持続可能な里山、里うみづくりのシンボルとして二ホンミツバチを掲げていることの意味が少しわかったように感じました。
タイミングが合えば活動場所の近くから漁師さんが船に乗せてくれるのだそうですが、今日はそれが叶わないとのこと。ちょっとだけ疲れが加わって、でも今日の作業に手ごたえを感じながら、帰りも30分かけて沖島漁港へ向かいました。島の外から道具も持参して整備にやってくるメンバーのみなさん、地元のみなさんの理解があってこその活動です。
目先の成果だけではなく、長く続けることの意義を感じた活動でした。