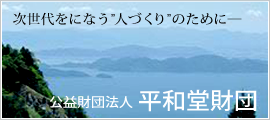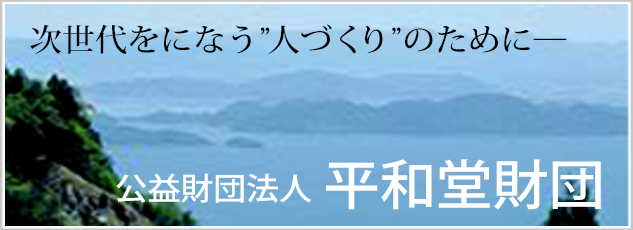在来種を育む水辺づくりと交流型里山イベント /Woodstick 桂川を守る会
事業の概要
Woodstick 桂川を守る会(旧Woodstick 上桂川)を守る会は、京都府左京区広河原にある空き家(通称トラウトタウン)を拠点に、さまざまな立場の人が連携して、桂川流域の環境保全と水源森林の保護活動を行っています。今回の事業では、この地域へ多くの人を呼び込むためにアウトドアサイト(フィールドアスレチック)とビオトープの設備を改修します。また、里山イベントを年3回実施して河川や水産資源の恩恵を享受し、交流できる場を提供します。

2022年8月7日、よく晴れた日曜日に京都市左京区広河原菅原町の広河原トラウトタウンへ向かいました。Woodstick 桂川を守る会が、地域の皆さんと協力して開催する、広河原里山フェスティバルなのです。

出町柳駅前からのバスに約2時間揺られ、菅原バス停を降りるとすぐにイベントの看板が出迎えてくれました。
橋の向こう側から音楽が聞こえて、たくさんの人でにぎわっている会場が見えました。

受付に行くと、すぐにWoodstick 桂川を守る会の代表、奥居 正敏さんが出迎えてくださいました。
別の団体であるWoodstickと桂川を守る会が連携して「在来種を育む水辺づくりと交流型里山イベント」という事業で2022年度の夏原グラント助成を受けています。今日は、その事業のイベントとして広河原里山フェスティバルを実施しています。

ウッドデッキでは音楽ライブ、クラフトブース、うどん屋さん。
デッキのテーブルとイスでは家族連れが音楽を楽しみながらお昼ごはんを食べています。
周辺のテントでは、アクセサリー、渓流釣り用のフライ、手作りパンなど、様々なお店が出ていました。

本部テントでは、ガサガサの受付が行われていました。
午前・午後で一回ずつ、すぐ前を流れる大堰川で生き物をつかまえる「ガサガサ」を行うのです。

「絶滅寸前種を探そう」というサブタイトルでしたが、果たしてこんな魚が見つかるのでしょうか。

また、炭火焼きのいいにおいがしてくる方向に行ってみると、アユを焼いているではありませんか。
これは、「アユの手づかみ からの 塩焼き体験」というイベント。対象は子どものみ、有料で2匹おまけありというのです。
大堰川に生け簀(す)を設えて、子どもたちが自分でつかまえてきたアユを焼いてもらえるのですから、絶対おいしいに決まっています。家族も、みんなワイルドに焼きたてのアユを食べていました。

炭焼きと同じエリアには、フィールドアスレチックの設備もあり、子どもたちが元気にチャレンジしていました。
また、園内にはビオトープが設けられ、美しいせせらぎに、バイカモ(梅花藻)が咲いています。
この園地のフィールドアスレチックやビオトープ、ウッドデッキの整備は、助成金で行われています。
歩きやすく、またフィールドアスレチックなどを整備することで、親子連れがここに来て自然に触れあい、過ごしやすい環境にするのが目的です。

ビオトープの流れで咲くバイカモ。

同じくよく見るとイモリも。
周辺にはトンボなども飛び回っていました。

音楽ライブの途中に、環境トークショーが始まりました。
Woodstick 桂川を守る会と連携している京都大学大学院の農学博士の貫名涼さん(桂川を守る会 環境学習専門委員長)と、窪田 孝幸さん(Woodstick 環境委員、桂川を守る会 魚類分布調査専門委員長)が、榛木 敏之さん(Woodstick 環境委員長)の司会で、環境にまつわることをお話されました。以下は内容のほんの一部をまとめたものです。
「このあたりの川にいる在来種は20種類くらい。アマゴは90%、アユは100%が移入種。特に希少な魚は、アカザやアジメドジョウ。
全国の一級河川の水の環境DNAを調べたら、魚が多い川は、上流に豊かな森がある川だった。山は海につながっていて、山が豊でないと川も海も豊かにはならない。将来、子どもたちが豊かに生活できるよう、山の環境を残したい。
今日、ここに遊びに来ているお父さん、お母さんたちは、自然に興味がある方だと思う。遊びの合間にこういうお話を聞いて、ぜひこれからも環境について考えてほしい。」

トークショーが終わったら、午後のガサガサの時間です。お子さんたちが集合し、記念写真を撮って出発しました。

ガサガサで生き物探しに専念したいチームと、時々川で流れて遊びたいチームに分かれて川へ。こちらは川に流れたいチームです。
大きな浮きボートに乗るか、救命ベストを着けるなどして、子どもたちは大人が見守る中、流れに乗って川を楽しんでいました。

ガサガサ専念したいチームは少し上流の橋まで行ってから川に入りました。
お父さん、お母さんに交じって、Woodstick 桂川を守る会の方や京大の貫名さんも参加中です。

みんな川を下流に歩きながら、ガサガサにチャレンジ。
「ガサガサは、あきらめたら終わりやねん!見つかるまで石の裏ひっくり返す!」と、指導の窪田さんが大きな声で子どもたちに伝えていました。
なるほど。
最初はこわごわ網を川に入れていた子どもたちも、下流の堰に着くまでには、次第にしっかりガサガサできるようになるのがわかりました。

最後に京大の貫名さんが「こんなんとれました!」と網をあげてみんなを集めると、なんととても珍しいヤツメウナギ。
魚に詳しい大人たちは、みんなとても興奮していました。
ヤツメウナギの口にはアゴがなく、相手に吸い付いて、口の中の針で体液を吸う、古い魚の形態がそのまま残っているのだそうです。

こちらは別のお父さんがつかまえた、ヨシノボリです。

すぐ前を流れる大堰川には、こんなにたくさん生き物がいるんですね。

川から戻ってきてよく見てみると、広河原トラウトタウンのビオトープのそばに網を張った池がありました。よくよく見てみると、たくさんの魚が群れています。これは大堰川に昔からすんでいるアマゴだそうです。
毎年秋には、この川と同じ水系にすんでいるアマゴから採卵し、孵化させて子どもたちに観察してもらい、その後大きく育ててから放流しているそうです。

釣りをしても一定の場所以外ではキャッチ&リリースしてください、とお願いをされていました。
今日、ガサガサに参加した親子は14組だったそうです。
専門家から指導してもらいながら、生き物をつかまえた体験は、大人になっても忘れないことでしょう。ゴミの落ちていない清流で遊んだ経験は、本当に貴重なものだと思います。
広河原自治会会長の新谷さんは「市からの援助がなくなり、一時期はどうしようと思われたこのイベントを引き継いでやろう、とWoodstickの皆さんたちが手を挙げてくれました。だからこうやって開催できてます。」とおっしゃっていました。
奥居さんはWoodstickというクラフト作家の会の代表で、空き家だった民家に手を入れて場所を作り広河原トラウトタウンいう拠点を作り、桂川を守る会の代表としても専門委員会のイベント企画委員会を担当し、この広河原里山フェスティバルをサポーターの皆さんと開催しているのです。
桂川を守る会には、他にも京都大学の貫名さんの環境学習専門委員会や、京北自治会長の上桂川利活用専門委員会など、たくさんの専門委員会に分かれて大学との連携なども行われています。
清流にゴミが落ちていないのも、地元の皆さんと会の皆さんが常に清掃を行っているからです。ほったらかしでは、こんなにきれいな川は維持できません。
イベント終了後、大堰川の川沿いを歩いていると、ミサゴらしき鳥を見かけました。自然が豊かな広河原と美しい大堰川は、地域の皆さんが協力して守っておられるんだな、と感じながら再びバスで帰りました。

Woodstick 桂川を守る会のイベント情報は以下のページからどうぞ。
▼ Woodstick 桂川を守る会(Facebook)
▼Woodstick(Facebookページ)