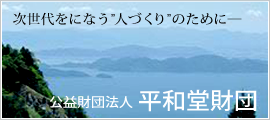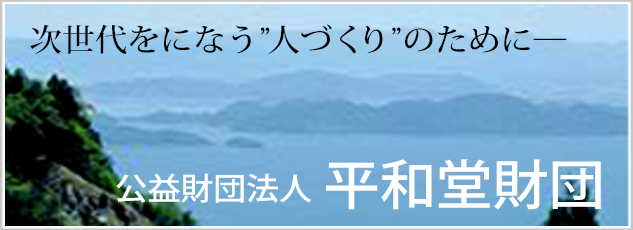森の保全及び公園の清掃活動 /みどりの会伏見桃山
事業の概要
みどりの会伏見桃山は、2001年から京都市伏見区の桃陽総合支援学校の敷地内の森(約2ha)と伏見城北堀公園の森(7ha)の保全活動を行っています。今回は危険木・倒木の伐採とその後の処理、伐採木を利用しての薪の製造とシイタケのほだ木の製造、シイタケ栽培、落ち葉での堆肥製造、子どもたちに呼びかけ、シイタケ植菌やタケノコの収穫作業を行ってもらっての森林維持体験、龍谷大学の大学生や、京都国際交流会館のボランティア団体と協力し、京都在住の外国籍の方に呼び掛けて一緒に倒木処理と薪づくりを通して森林維持を体験をしてもらう、ということを予定しています。

2022年6月18日(土)、みどりの会伏見桃山の皆さんの活動を取材するため、京都市伏見区の京都市立桃陽総合支援学校と桃陽病院の敷地内にある森を訪問しました。
この日は、みどりの会伏見桃山の皆さんが、龍谷大学環境サイエンスコースの谷垣さんの担当するゼミ生の野外体験の指導をすることになっています。

龍谷大学の学生の皆さんはまず受付を済ませ、手を消毒しました。
みどりの会伏見桃山ののぼりが立っています。

お茶、熱中症対策の飴、虫よけスプレー、そしてヘルメット。
これらを装備したら、プログラム開始です。

谷垣さんによる趣旨説明と、みどりの会伏見桃山の紹介のあと、会の代表の徳丸さん(左)と、薪づくりの指導担当の森本さんがご挨拶。
「今日は森を回って薪を集め、薪割りをします。
森の手入れは竹の駆除から始めました。この森には、時々オオタカが来て狩りをしているようです。タヌキは見かけますし、穴があるのでアナグマもいるようです。全国で問題になっている、シカ、イノシシはいません。
今はスズメバチが活動を始めていますし、ヘビもいます。もしもスズメバチに刺されたら、ポイズンリムーバーを使ってください。」
森本さんから、いろんな注意喚起をされ、身が引き締まります。
その後は、一列になり施設の脇の道を下っていきます。


この施設は、もともと実業家の別荘だったということで、時々その名残が見られます。石橋も、優雅なデザインですね。

みどりの会伏見桃山の皆さんが定期的に手入れをされているため、道も歩きやすく、森の中も明るい印象です。

しかし、コロナの影響でこの森に入れなかった時期に、孟宗竹の筍がこんなに育ってしまいました。
今日の午後は、この孟宗竹の伐採も行う予定とのことでした。

ここで学生の皆さんが背負っている、黄色いカゴをご注目ください。
間伐された木材が、適度な長さに玉切りされていて、道のそばに置いてあるで、それを拾って帰るのが今回の使命なのです。

結構な重さがある丸太が入りました。
下ってきた坂を、今度は登らなければなりません。機械を入れて運べないため、森からの木材運搬は人力に頼らざるを得ないのです。

上まで運んできた丸太は、細かく割って薪にします。
薪割りの手順や、注意点を、みどりの会伏見桃山の藤井さんと、森本さんが実演しながら説明します。
これは、斧では割れない場合、楔(くさび)をハンマーでたたいて食い込ませているところです。

楔2本で割れました。
まず、ハンマーや斧を使う前に周囲に人がいないことを確認し、また斧やハンマーがすっぽ抜けないよう、滑り止めのついてない軍手を使わないことなど、大けがに通じるので注意しなければなりません。頭に当たる危険もあるので、ヘルメットは必須です。周囲を通りかかる時には、声を掛けて。

こちらは子どもでも薪割ができるように考案されたという、キンドリング・クラッカーです。
斧を使わず、ハンマーでたたくと、割れるような道具です。これなら、と女子学生もチャレンジしています。

そのうち、丸太運びの第二陣が出発しました。しばらくして帰ってきたら、「重い!」と倒れ込む人もいるほど、かなりきつい様子でした。お疲れさまでした!

一方、みんなが薪割りしているところから少し離れた場所では、お昼ごはんの準備が着々と進んでいました。落ち葉や細かく割った薪でご飯を炊き、カレーを作るのです。薪での焚き付けに苦労しながらも、学生の皆さんが火の番をしていました。
ついにご飯とカレーが完成しました。


皆さん持参した食器を持ち、列になって盛り付けしてもらっています。私もごちそうになりました。おいしかったです!
みどりの会伏見桃山のメンバーの奥様から食後のスイーツの差し入れまでいただき、すっかりくつろいでから、午後の活動が再開されました。
私はここまでで、学生の皆さんよりも一足先においとましました。ここから少し離れた、伏見北堀公園が、みどりの会伏見桃の本拠地なので、案内していただくのです。

藤井さんの奥様の車に乗せていただきました。こちらが、伏見北堀公園です。

もともとは伏見城の堀だったところが、公園として整備されているそうです。なので、公園に行くには階段を下っていきます。

ここは、みどりの会伏見桃山の皆さんが、伐採した枝などを積み上げているところです。こうしておくと、市のほうで搬出してくれるとのこと。

この道は堀の底にあたる、一番低いところにある公園の遊歩道です。
道沿いのアジサイはみどりの会が手入れしているそうで、花が終わった後の花柄もいちいち手で摘んでいく必要があり、結構たいへんだそうです。

公園内で弱っている松。「これもゆくゆくは伐採しなければ」と藤井さん。常に公園内の状態に目を配っておられます。

こちらは公園の隅のほうに作られた、落ち葉を堆肥にする場所です。会の皆さんの手作りだそうです。
舗装路に落ち葉が積もった状態のところに雨が降ると、滑りやすくなり危険なので、集めてここに運んでいるということです。
ここには、子どもたちがカブトムシの幼虫をとりにやってくるそう。子どもたちからすると、ここは宝の隠された秘密のスポットでしょう。

また、この花壇も、会の花壇担当の皆さんが手入れされている場所です。

女性メンバーのお一人が「園芸に興味を持っていたのですが、学校に通って木について学ぶうちに木のことも好きになり、また、友人がみどりの会伏見桃山の会員だったので、その人からのお誘いで入会しました。
花壇では、蝶が来る花を植えるなど、テーマを決めて花を選ぶ計画を考えていて、とても楽しみです。
以前は種から育てた苗を植えるしかありませんでしたが、
夏原グラントで助成金をもらえることになり、いろんな種類の苗が買えるので、とても喜んでいます。
花壇で手入れをしていると、通りかかる人から声を掛けられることもありますし、子どもさんにも意識して声を掛けるなど、人とのふれあいも心がけています。それも活動のよいところだと思っています。」と話してくれました。

この道は、一番底の道ではなく、少し上のほうにある道で、公園の周囲をぐるりとめぐることができます。ランニングや散歩をする人に人気のコースだそうで、確かに気持ちがよくて人通りが途絶えない道でした。

ここは、会の皆さんが花を植えようと畑にした場所だそうです。藤井さんによると「笹の根がいっぱいあって苦労しました」とのことです。

公園整備のための道具入れもありました。
公園内を通り説明をしてもらっていると、藤井さんは一本の桜、道のそばの樹木などを見ながら、とても大事そうに説明をされます。その様子から、長年愛情をもってこの公園の手入れをされきたことがとてもよく伝わってきました。
もちろん、管理には専門家が仕事として関わることが基本ではありますが、市民が公園を利用するだけでなく、自ら愛情をもって世話をするということも大切ですね。この北堀公園は、行政(と業者)、市民(みどりの会伏見桃山の皆さん)が協力しながら守っておられます。
これからも、みどりの会伏見桃山の皆さんが楽しみながら、長く活動されることを期待しています。