サケ環境保全啓発活動 /由良川サケ環境保全実行委員会
事業の概要
京都府を流れて日本海にそそぐ由良川にはサケが産卵に遡上してきます。そのサケから卵を取り出し、受精させ、希望する子どもたちに自宅で孵化まで世話をしてもらい、由良川に放流します。

2025年3月16日、由良川サケ環境保全実行委員会が実施する事業「サケ環境保全快活活動」のプログラムで、「綾部サケ放流まつり」を行うとのことで訪問しました。
もともと京都府の主導で実施されていたサケの放流事業。ここに小学生の参加を引率していた実行委員会有志が、その事業終了後に食料政策だけではなく、ふるさとの川を美しく守り流域の環境に対する意識を高め、また子どもたちのふるさとに対する郷土愛を育みたいとの思いを込めて、自主的に継続して放流まつりを実施してきたという経緯です。
例年、毎年10月下旬、回帰サケ(親サケ)の採捕・採卵をし、卵を受精させ、肉眼で卵の膜から魚の目が確認できる発眼卵までを実行委員会が育て、他地域からの移入卵も加えて各家庭や学校などの希望者に配ります。地域の子どもや大人が、自分の手で卵から放流までの稚魚を飼育するという体験をします。その稚魚を放流するのが、今回のイベントです。
当日はあいにくの雨でしたが、予定通り開催するとのことで、会場の綾部市の由良川花庭園へ向かいました。
到着すると、すぐに開会式が始まりました。
会長の佐々木さんから、今回のサケ放流祭りについて説明がありました。

毎年、由良川サケ環境保全実行委員会では、由良川での採捕・採卵と新潟県から移入している発眼卵を育てて放流しているけれども、今年は新潟から全く入ってこなかったとのことです。そのため、今年は市民の飼育参加もできない状況の中、地元で捕れた地場卵のみで今日を迎えることになり、とても残念だとの思いを告げられました。それでも、こうやって、雨降りの中、関心を持ってくださったみなさんが集まって地場卵のみの放流ができることに感謝しておられました。地場卵を育てるにあたっては「サケのふるさと由良川を守る採捕者の会」と「牧川養殖漁業生産組合」の協力でできたとのことです。
今日放流する稚魚です。

「これだけ大きく育つのは、各家庭や学校などで飼育するのと違い、さすがプロという感じです」とのことです。最初に見た時、稚魚とはいいながら大きいなあと感じたのですが、そういう経緯があったのですね。
開会式が終わり、放流する場所へ移動していきます。
少し雨が強くなってきたようです。

先に、稚魚を乗せた軽トラが放流場所近くまで行っていました。そこでバケツを下ろし、それぞれに水を入れていきます。子どもたちも興味津々で集まってきました。


そして、稚魚です。少し離れて見ていましたが、大きさと元気良さが伝わってきました。

バケツに入った稚魚を見て、子どもたちもテンションが上がってきたようです。稚魚が入ったバケツを、早く早く!という感じで、どんどん手を出して持ちあげています。


雨が強まってきました。
放流するのは、川が曲がって溜まりとなっている場所です。堤防から少し降りなくてはなりません。雨のこともあり足元が緩んでいますが、子どもたちはみんな気を付けながら水辺に並びました。
そして会長の佐々木さんの掛け声「帰って来いよ~」で、一斉に放流です。

子どもたちも、みな口々に「帰って来いよ~」と思いを乗せています。
堤防をもう1回往復して、計2回、子どもたちはサケの放流を体験しました。
例年、各自家庭や学校で育てた稚魚を放流してるので、必ず数人の子どもたちは泣きながら、中には放したくないという子どももいるそうです。
そして大人も。

無事放流が終わって、本部に戻ってみると、なんとふるまいが。
大きなお鍋にたっぷり具の入った「あったか鍋」を、地元の方が準備してくださっていました。


一口一口と口に運んでいただいていくたびに体が温まり、雨で少々冷えていた体が喜んでいます。大人も子どももみんなテントの下、肩を寄せ合って、あったか鍋をいただきました。
閉会式もテントの中。それでも、放流ができたことの喜びに満ちていました。
会長の佐々木さんが、みなさんへの感謝と帰ってくるサケへの期待を込めてあいさつされました。
「サケは育った川のにおいを覚えていて、それを頼りに帰ってきます。なので川のにおいが変わらないよう、今のきれいな川のままでなくてはなりません。そのためにも、このいい環境を保っていかなくてはなりません」。この言葉が、今日のイベントを通して子どもたちの心に留まったのではないかと感じました。

今回、移入卵が手に入らなかった原因としては気候変動(温暖化)の影響も考えられますが、その他飼育中の停電などのアクシデントもあったそうです。放流できる稚魚が少なく、放流まつりの日の雨。でもそれら全部含めて、自然の中で活動している証だともおっしゃっていました。
終了後に、地元のラジオ局の取材を受けている、会長の佐々木さん。

来年、卵がどうなるかはわからないけれども、サケの飼育・放流事業を続けてきたいという意欲は、決して失っていないとのこと。自然の中での活動なので気象や環境の状況などにより、予定通りに行かないことはたくさんあります。それでも思いを胸に、長年取り組んでこられたことに頭が下がります。これらの活動が大きな成果となって地域に帰ってくることを願って、会場を後にしました。

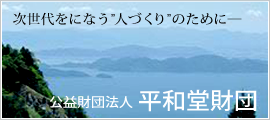

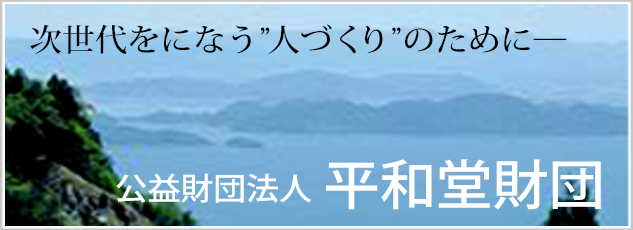

素晴らしいリポートです。
実行委員会の思いや参加者の思いを丁寧に表現していただいています。
ありがとうございました。
自然の摂理と戦うのはつらいですが、人工授精などサケの生存領域に少しの手助けは継続して行おうと思います。