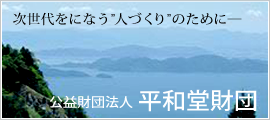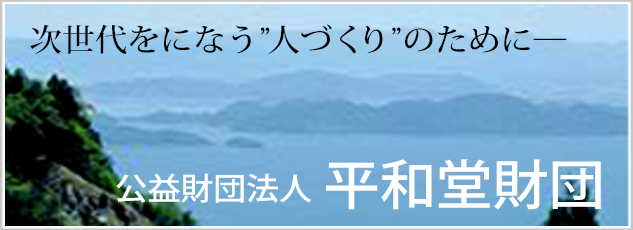バンブードームを作って竹工作を楽しもう! /籔の竹ぼうき
事業の概要
京都府向日市の竹林整備で出る竹を使って、子どもや大人が楽しい野外活動を行うことで、美しい竹林のよさを感じてもらい、竹林整備への参加へ繋げていきたいです。

2024年10月19日、籔の竹ぼうきの竹林整備活動を訪問しました。
向日市駅からバス移動となる向日市物集女町の竹林が活動場所です。すぐ近くには小学校があり、竹林の遊歩道は子どもたちの通学路になります。この日は運動会が開催されており賑やかな声が響いていました。

入口近くには竹で作られた花鉢に“籔の竹ほうき”の表記があります。

上がってすぐの右側が入口、遊歩道は整備されています。
メンバーは近隣や県外から全員で10人、この日は7人と子ども2人が参加していました。
「籔の竹ぼうき」の活動は当初、“藪のそば”というグループ活動で遊歩道の清掃と整備で出た竹を燃やすなどの内容だったそうです。燃やすだけではなく竹をもっと有効活用できないか?と、切った竹でほうきを作ったことがきっかけで“藪の竹ほうき”の活動がスタートすることになったそうです。
活動日は毎週木曜日と第3日曜日です。
活動目的は、間伐竹の有効利用・竹林遊歩道美化・間伐材を利用した竹ぼうき作りなどのワークショップによる地域の世代間交流として活動されています。

この日、まず初めに竹林奥の整備で出た竹を燃やすために消防局へ電話で許可を取られていました。次に、竹林には蚊が多いので人数分の蚊取り線香の準備をします。



遊歩道に沿った場所には最初に整備された休憩場所があり、竹を使った作品がたくさんありました。
落ち着いた静かな場所で、英会話教室や近隣住民やこども園が散策されることもあり解放されていますが、使用は許可制にして子どもだけでの立ち入りがないように管理されています。
今年度の活動として、竹ドームを作る計画が進んでいました。休憩所から奥の竹林を間伐し切株や廃竹を撤去して設置場所をつくり、竹ドームの屋根を付け、中にテーブルと椅子を設置する予定だそうです。


整備活動場所へと進んで行きます。

途中には竹を使ったかわいい作品がありました。


切った竹の節に溜まった雨水で悪臭とボウフラが発生します。
何か予防できないかと、水面に油を落として油膜をはりボウフラを封じ込める方法を試したそうですが生命力は強く、まだ解決方法が見つからないそうです。

活動場所へ到着しました。

夏原グラントロゴを使った手製の看板が付けられていました。


代表理事寺﨑さんが制作した模型を見て、参加者へも出来上がりのイメージが伝わり、今後について色々な話が盛り上がりました。ですが、一度整備した場所が夏の台風や大雨で再度整備が必要となり、予定より少し遅れているとのことでした。

山ほどある廃竹の処分作業の効率を上げるために助成金で購入した移動式の小型粉砕機です。
この日は雨が降っていたので動いているところは見られなかったのですが、廃竹が腐るまで待たずに一気に大量に粉砕することができ、整備を進めることができるので助かっているそうです。

落ちている竹の横枝を切り取り、なるべく一本の竹として処理をします。
助成金を活用して購入した電動のこぎりを使われていました。
手ばさみで切っていたので手の負担も減り作業効率が上がったそうです。

横枝を処理した竹を一カ所に集め、そこからさらに小さく分類していきます。

細かくした竹は枯れるまで待つことができないので、助成金で購入した無煙炭化木器本体を使い燃やしていくのですが、器の形が広がっているので酸素が中で回り煙が出ない構造で、二酸化炭素排出も少なくなり環境への負荷を減らすことができるそうでした。

燃やした熱を使い、竹の先にマシュマロを挿して焼いて食べるなど、お孫さんたちの楽しみも準備されていました。

もちろん食べた後は、竹の枝を振り回しておもちゃに。
竹と竹が当たる音は心地のよい響きでした。

しっかりと水をかけて鎮火させます。

後は蓋をかぶせて完全消火に努めておられました。

以前のイベントで使われた竹です。
この竹の中でお米を炊き、炊きあがったご飯に直接カレーを入れ、お椀としても使ったそうです。


さらに奥に進むとまだ整備されていない場所があります。放置されている場所と整備された場所で違いがよくわかりました。

整備された竹林と放置竹林を比べ想像すると、これまでの活動量や作業時間から放置竹林をなくすゴールまで先が見えない膨大な活動であると感じました。籔の竹ぼうきのメンバーは、竹を使ってそれぞれがやってみたい活動をすることを楽しんでおられ、子どもや地域の方に竹の美しさを知ってもらい安心して竹林を散策してもらうなどワークショップを取り入れて野外活動の楽しさを伝えたいと話されてしました。
美しい竹林が次世代へとつながっていくことを願っています。