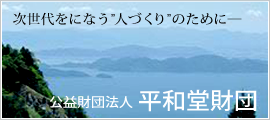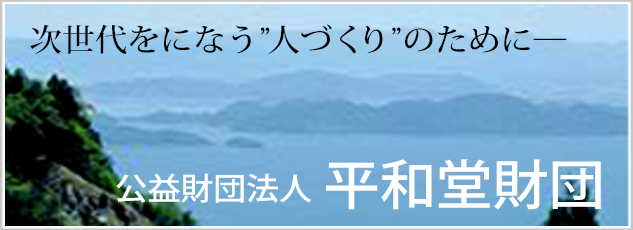有機農法拡大 /立命館大学経営学部プロジェクト団体 丹後村おこし活動チーム
事業の概要
京都府宮津市日ケ谷の農地で、中山間地域における有機農法による農地を拡大させたいと考えています。農業の効率化のためICTを活用し、自分達で栽培したお米を使って地元の方といっしょに味噌をつくり販売します。

2025年1月26日、立命館大学経営学部プロジェクト団体 丹後村おこし活動チームが実施する事業「有機農業拡大」のプログラムで、味噌加工作業を行うところを見せていただくために訪問しました。有機農法を定着させるためには、米の生産だけではなく加工品製造まで視野に入れた取り組みが必要とのことで、地域住民の方々の指導も仰ぎながら加工施設で味噌の加工に取り組んでいるものです。
写真は、作業をおこなう加工施設の前から撮ったものです。中山間地に田畑が広がっています。
立命館大学経営学部プロジェクト団体 丹後村おこし活動チームは、2004年に地方での活動を通して経営学の学びを深め、これからの社会の在り方を考えることを活動理念として発足し、多様なプロジェクトに取り組んでいます。自然環境内での物質代謝による持続可能な社会システムの構築について、座学と実践活動を組み合わせて活動しているそうです。現在は、経営、政策科学、経済、理工、食マネジメント、情報理工、総合心理、文学の8学部の学生が在籍し、学部横断的な活動となっています。
ここが、今日の作業が行われるのは地区公民館に隣接する「日ヶ谷の里センター」です。

「今日の作業」なのですが、実は作業は前々日の1月24日から始まっています。
味噌づくりの手順は「大豆を水で洗い水につける」→「大豆を煮る」→「大豆をつぶす」→「塩きり麹(塩と麹を混ぜたもの)と混ぜる」→「味噌をボール状に丸める」→「味噌樽に味噌を詰めていく」。とても1日でできるものではありません。特に「大豆を水で洗い水につける」→「大豆を煮る」には時間がかかります。全員で13名が、前々日と前日から参加の2グループに分かれて、会場に集まり作業を進め、そこで宿泊。今日も朝早く起きて作業をされていたそうです。
当日、お邪魔したときには味噌づくりの工程としては、ほとんど終わった状態でした。
お願いして、作業中の写真をお借りしたので、それを紹介します。
「大豆を煮る」

「大豆をつぶす」。今回はミンサーを使っています。

「塩きり麹(塩と麹を混ぜたもの)と混ぜる」

「味噌をボール状に丸める」

「味噌樽に味噌を詰めていく」

表面に空気が触れるとカビが生えてしまうので、上から塩をかけ、ラップで覆います。

味噌樽がたくさん並びました。ここから奥の保存室へ運び、発酵・熟成が進むのを待ちます。味噌が出来上がるまではまだまだ時間がかかります。

作業は昼前に終わりました。
加工場はきれいに掃除し、整頓。

外で、使っていた長靴を洗っています。

今回、学生たちの作業を指導・応援されている地元のNPO法人美しいふるさとを創る会で、当日来ておられた松田賴彦さんにお話を伺いました。松田さんは丹後村おこし活動チームの発足当時から、学生を受け入れておられるそうです。長年続いている活動なので、このチームを卒業した方が、訪れてくることもあるそうです。
作業が終わった後は、地元の方と昼食。近くの方がお蕎麦を持って来てくださいました。そして自分たちで作った有機米でおにぎりを作り、これも自分たちで作った味噌が添えられていました。どちらもとてもやさしい味で、おいしくいただきました。
その後、学生のみなさんから、自分たちで進めている研究について報告があり、地域の方たちも関心を持って聞き入っていました。

まずは、多様な学部からこの丹後村おこしチームに参加されているということに驚きました。研究を進めるゼミのような、関心を持った人が集まってくる部活のような、それぞれがまじりあったような雰囲気です。参加の動機もまたそれぞれなのでしょうが、ひとつのテーマに対して異なる専門性で取り組むことに意義がありそうです。
そして地域の方々は、学生のみなさんが、毎年毎年メンバーが交代しながらも、継続して来てくれていることを喜んでおられる様子です。地域のいろいろなことを話しながら、互いにうなずきあっているのが印象的でした。