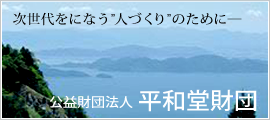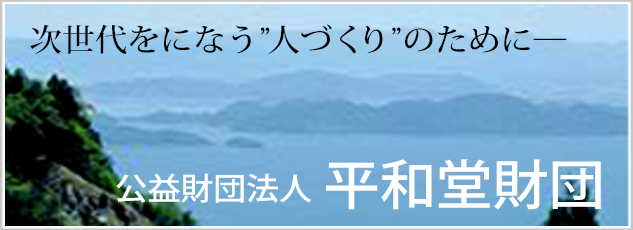21くろやま塾の活動 /21くろやま塾
事業の概要
京都府右京区の京北地域にある山国地区の休耕田を借りて、地元の子ども達にサツマイモ栽培、川での自然観察会、秋祭参加、しめ縄づくり、と、地元の自然環境や伝統に親しみます。

2024年9月14日(土)、晴天に恵まれたこの日も35℃を超える猛暑日となりました。そんな中、京都市右京区京北比賀江町にて、旧京北町内を中心に活動される「21くろやま塾」のさつまいも掘りが行われました。
21くろやま塾は、1995年に旧山国小学校区の住民が中心になって発足した「山国塾」から始まる活動です。小学校の土曜学習を中心に地域教育の場づくりを担う団体として活動してこられました。1999年の小学校統廃合とともに活動エリアを広げ、京北地域全6地区のうち、黒田地区と山国地区で活動を行われています。
2020年度、京北地域の全小中学校が統一され、小学校と連携しながらの活動状況にも変化が訪れ、2022年度からは夏原グラントファーストステップ助成を受けるなどして活動を継続されています。


年間通して活動されており、サツマイモの定植と草刈り等管理、収穫を行う農業体験、夏場の川と山それぞれをフィールドにした観察会、冬に行うしめ縄・わら細工づくりの伝統体験と、季節ごとに自然に学び親しむ活動を実施されています。
この日は、6月2日の農業体験で植えられた約1000本の芋苗が収穫をむかえた芋掘り体験でした。京北地域からの参加者の他、伏見区をはじめ市街地からも参加者があり、17組55名が集まりました。学校との連携は現在も継続されており、後日、京都京北小中学校9年生の生徒たちも芋掘り体験に訪れたそうです。
前述したように、猛暑日となった当日。活動中の随所に暑さ対策を取り入れて運営されていました。まずは日よけテントを設置し、活動の説明や休憩時など小まめに立ち寄れる日陰を作られました。
参加者に提供できる冷たいお茶の準備や塩タブレットの配布などで熱中症に配慮された他、ペットボトルの氷や保冷剤を準備し、参加者の休憩時に手や首を冷やす道具として貸し出すなどの工夫をされていました。事務局長の益田さんによると、これまで農業体験に必要な農機具等のほか、ウォータージャグや保冷剤など暑さ対策の用具類もスタッフの私物などで対応されてきたそうですが、助成金を活用した備品や消耗品購入でまかなえ、十分に準備できたとのことでした。




芋掘りの作業は、掘るだけではなく、ツル切りとマルチシートはがしもみんなで行いました。
それぞれの作業を始める前にメンバーの方からお手本を見せてもらい、作業の注意点などを詳しく共有しました。鎌などを使う作業は大人が行うように、ケガをなくすように丁寧にガイダンスをされました。広い芋畑でしたが、大人数で作業することであっという間に作業が終わっていきました。



掘り出し方もまずは実演を見て学ぶ
子どもたちの参加も多く、芋掘り中は楽しそうな声が響きました。「お気に入りの芋を選んで後で紹介してね」と塾長 堀本葉木さんが開会時に案内されたこともあり、それぞれが選び抜いたサツマイモを大事そうに抱えていました。掘り出した芋は参加者のお土産にもなりましたが、21くろやま塾の活動の1つとして、京北地域の秋祭りでの焼き芋販売に活用されているそうです。



設立から30年、21くろやま塾は数回の代表変更の後、昨年度の交代で若い世代へ引き継ぎ、現在の体制となっています。当初から変わらないのは、地域教育のために設立された団体として、地域とのつながりを大切にされている姿勢だそうです。焼き芋の販売も、地域の恒例行事に参加し、地域の方たちとの交流機会として重視されているということでした。他にも、活動情報とイベントの告知を載せた「21くろやま塾NEWS」を発行し、京北地域の新聞への折り込みもされています。地域に向けて活動情報を発信し、地域の方に知ってもらえるように、地域の一員として認められていくように、という働きかけとして意識されているとのことでした。
活動の運営は、行事毎に役員を含めスタッフ7~8名で実施。会員こと“塾員”は20数名で、以前から活動を担われてきたメンバーに加え、新たに加わられた40代や50代の方も多いそうです。京北地域の出身者や住民が中心で、地域居住の塾員や参加者も増えてきているとのことです。
代替わりして長く続いている活動の工夫を知りたくて、最初は活動の参加者だったという塾長の堀本さんにどうやって仲間になっていかれたのかを尋ねたところ「活動に来ていると自分でも農作業のことなどもっと詳しくなりたいと感じてきて、そのころに友人と誘い合って『ちょっと入ってみようか』と塾員になった」とのことでした。
先輩メンバーからの「来れるときでいいよ、ゆるくやっているから」という言葉と、地域に根差した活動で地域の他の行事でもスタッフの方と出会い、つながりが生まれてきたことなどにも背中を押された、ということでした。
現在は参加人数が増えることもある定例の活動がスムーズに実施できるよう、役員会で事前の段取りをしっかりとしているとのこと。塾員の研修としての野外活動なども年間行事として行い、塾運営の基礎となっているようでした。「いずれは京北全域をフィールドにした活動に成長したい」と塾長の堀本さん。毎年の活動で着実に広がっているようでした。
※冒頭集合写真:21くろやま塾提供