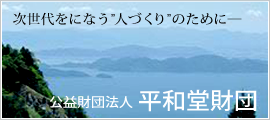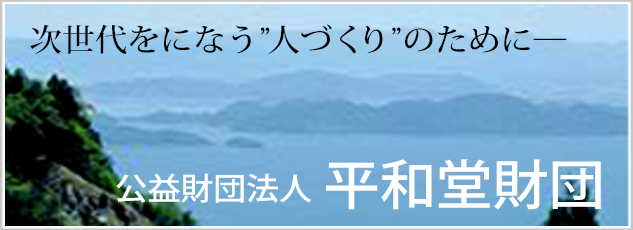コバノミツバツツジとアカマツの保全と育成を進めて、市民が楽しめる豊かな森林にしよう /一般社団法人 宇治きこりの会
事業の概要
地域の山“谷山サブロー”の樹木の手入れを行い、更新が行われる健全な森づくりを目指し活動しています。シカの食害の防止とともに、低木コバノミツバツツジの保全、アカマツの枯死木処理に取り組み、山林に親しむ企画を行っています。

2025年5月29日(木)コバノミツバツツジとアカマツの保全活動をされている「宇治きこりの会」の活動にお邪魔させていただきました。
活動拠点がある炭山は、仲間たちが所有している私有地です。宇治の北端に位置し、山を越えると大津市南郷と隣接するところにあり、今から813年前の鎌倉時代に書かれた鴨長明の随筆「方丈記」にこの地名が記されており、その麓には京焼の窯元が多く軒を並べる、緑豊かで静かな里山です。


炭山の土壌は堆積土で、斜面は急な所が多いため樹木の根が張りにくく、新たな後継樹が育ちにくいという特性があり、まとまった雨が降ると薄い土壌が流れ出し、山のあちらこちらで山崩れが起きます。元々、産廃業者が廃棄場に使っていた山なので、山の中腹あたりには土を積んだだけの場所があり、その下には住宅地があるので雨が酷くなるとその土砂が一気に流れ出る危険性があります。特に十数年前に発生した豪雨災害をきっかけに近隣地域住民の防災意識が高まりました。
当時、団体代表自身が別の団体で災害ボランティア活動をしながら各種の勉強会や参考文献など読み進めていくうちに、災害の元凶となる荒れた里山をどうにかしなければという思いが強くなり谷山を所有したそうです。
「宇治きこりの会」は近隣や京都から集まる15人で構成され、毎週木曜日に集まれるメンバーで崩れた道の整備や樹々の食害のチェックなど山の管理をされています。


炭山にはコバノミツバツツジや赤松の群生地がありましたが、マツクイムシなどの虫によって松枯れやナラ枯れをおこし、残っている松も元気がないように見えます。また、幹が2~3㎝育つために30年、40年かかるコバノミツバツツジは鹿の嗜好に合うようで、食害がひどいとお話しくださいました。鹿は目についた美味しくて柔らかい木は全て食べつくすため、訪問した時も新たなシュートが出る時期でしたが、その芽はあちこちで食べられていました。


一方、鹿の嗜好に合わない木は成長が早く、食害もないので高く枝葉を大きく広げています。すると、成長の遅いコバノミツバツツジなどの下層に生える植物には日の光が当たらず、成長しづらい状態にあります。




この日の作業はコバノミツバツツジの生育を鹿の食害から守るため群生しているところの位置を確定するというものでした。獣道を利用した遊歩道を歩きやすくするため枝払いしながら進み、急勾配の斜面に生えるコバノミツバツツジが群生する場所の外周を、黄色いテープで木にポイントを付けていきます。足元が不安定なため、体幹を使い作業をします。1,2時間かけ、周囲173mのポイントを付け終えました。
夏原グラントの助成金を使い、後日このポイントを囲むように金属柵の設置をします。



山頂付近にある赤松は幹に虫が入りほとんど切り倒されましたが、まつぼっくりから自然に発芽し、それをネットで囲い鹿の食害から守っているおかげで50㎝ほどの苗がたくさん育っていました。将来的に赤松を増やし、そこから松茸もとれるようになればいいな、とこれからの展望をお話しくださいました。



そして助成金で設置した柵で鹿の食害から守り、桜の季節が過ぎたころに満開を迎えるコバノミツバツツジの群生が近隣住民のみならず、炭山を訪れる人たちの目を楽しませる、そんな山にしていきたい。そのためにはこの活動を続け、続けるための後継者を育てなければ、と力強くお話しくださったのがとても印象的でした。